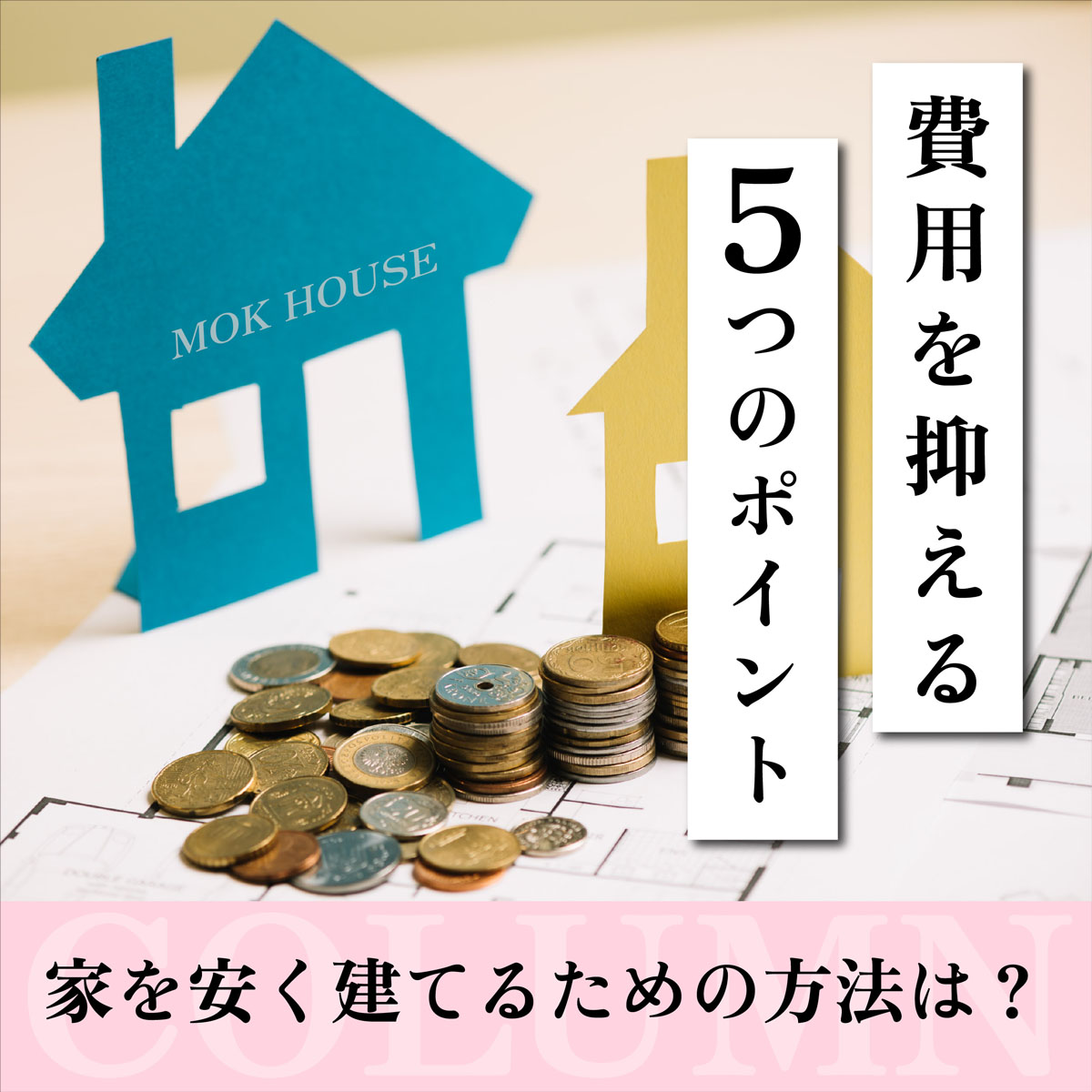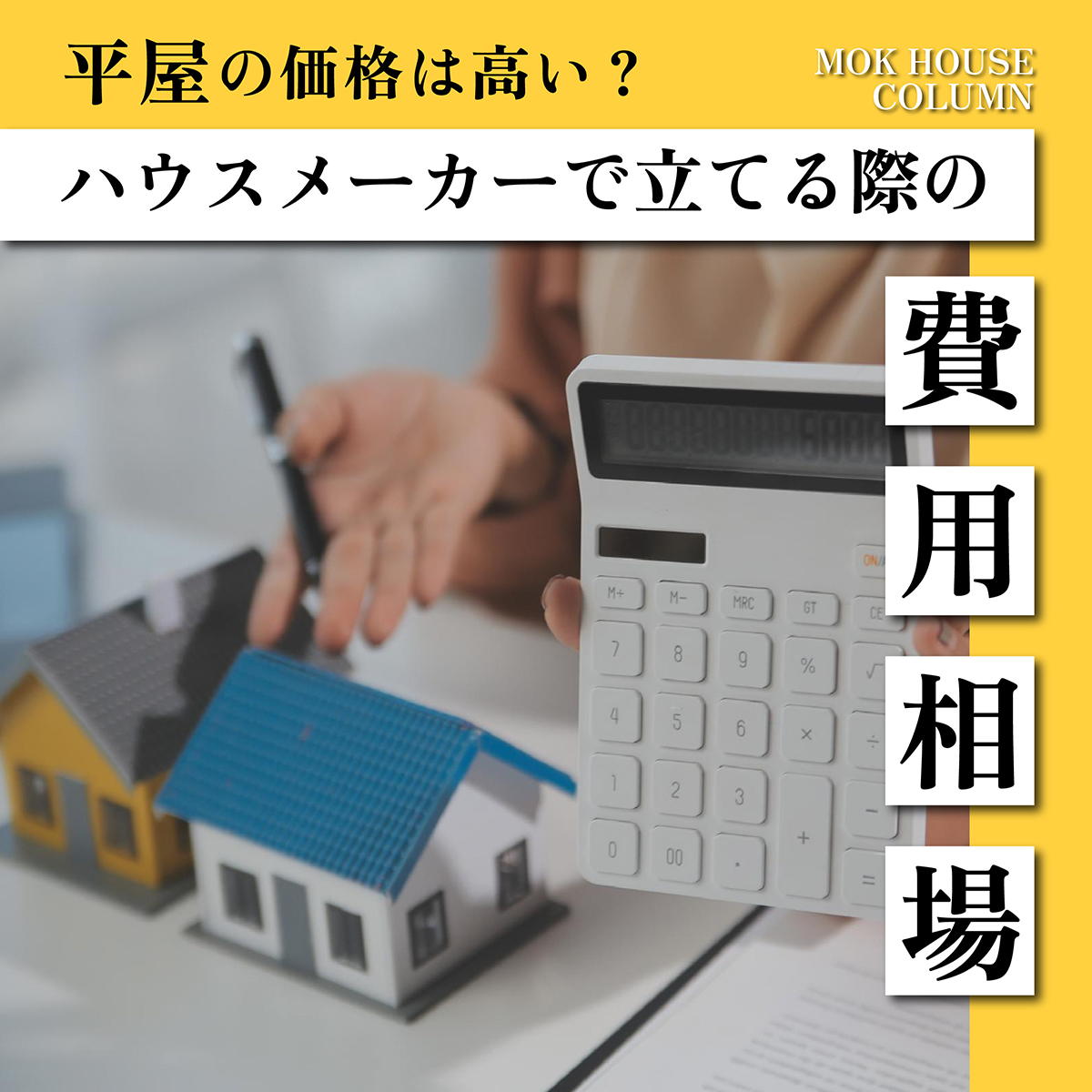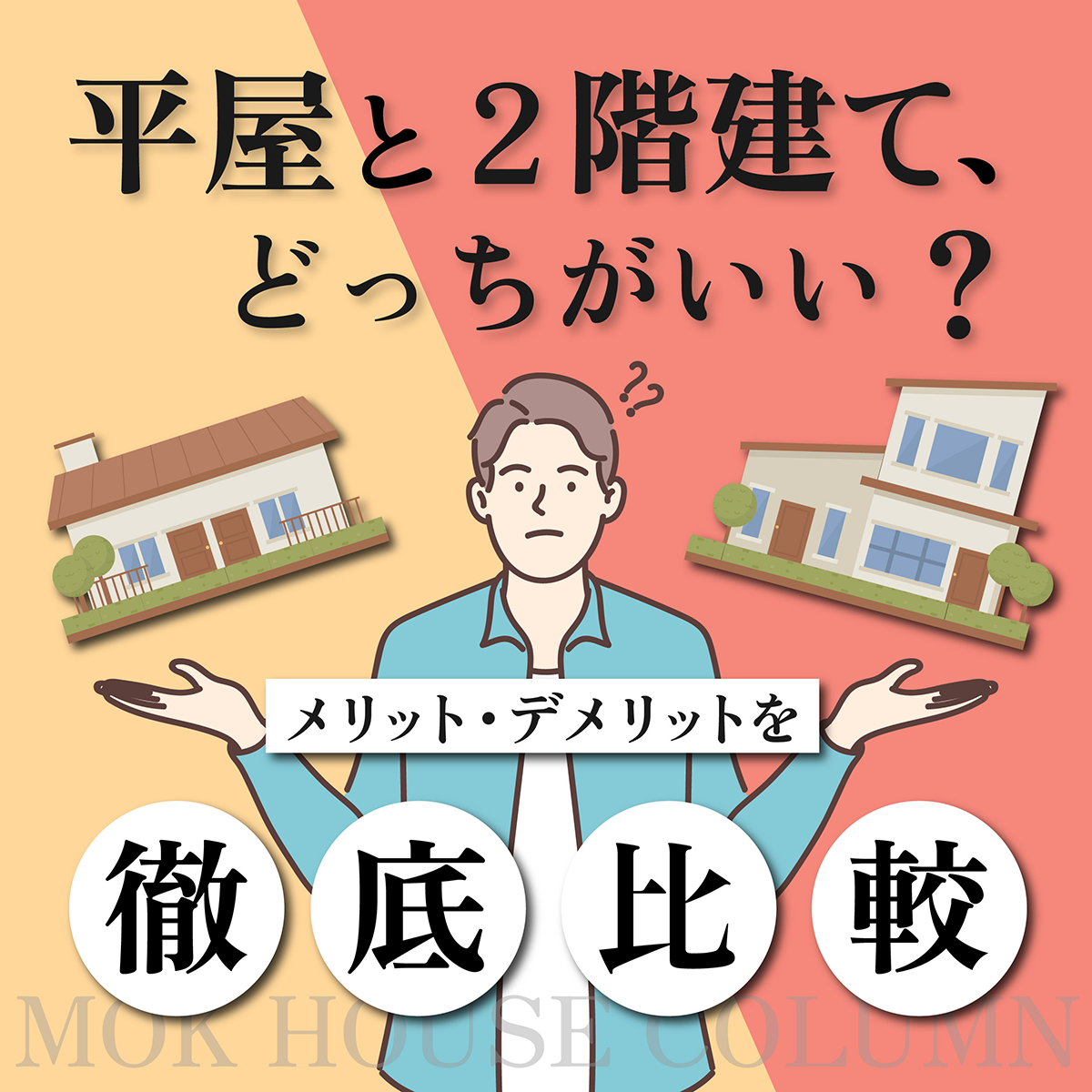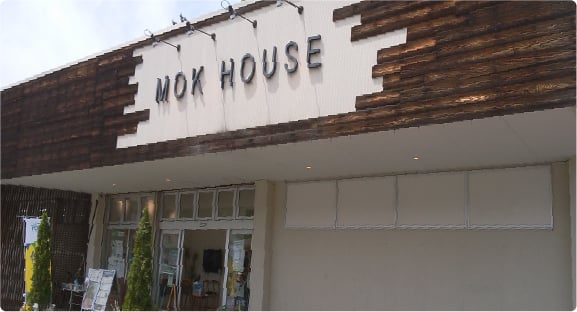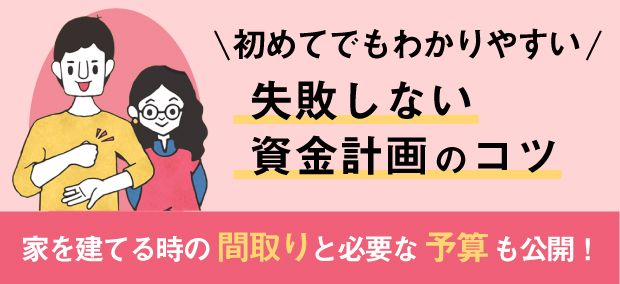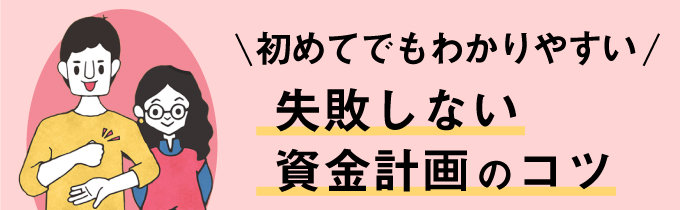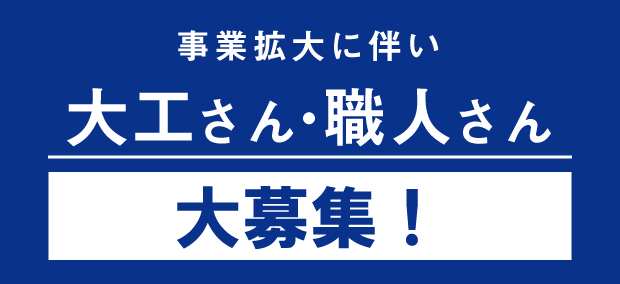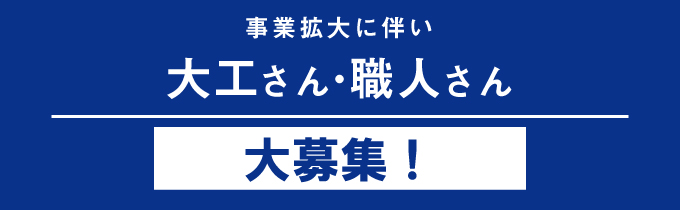家を建てる費用を抑えるには?ローコスト住宅で賢く建てる方法
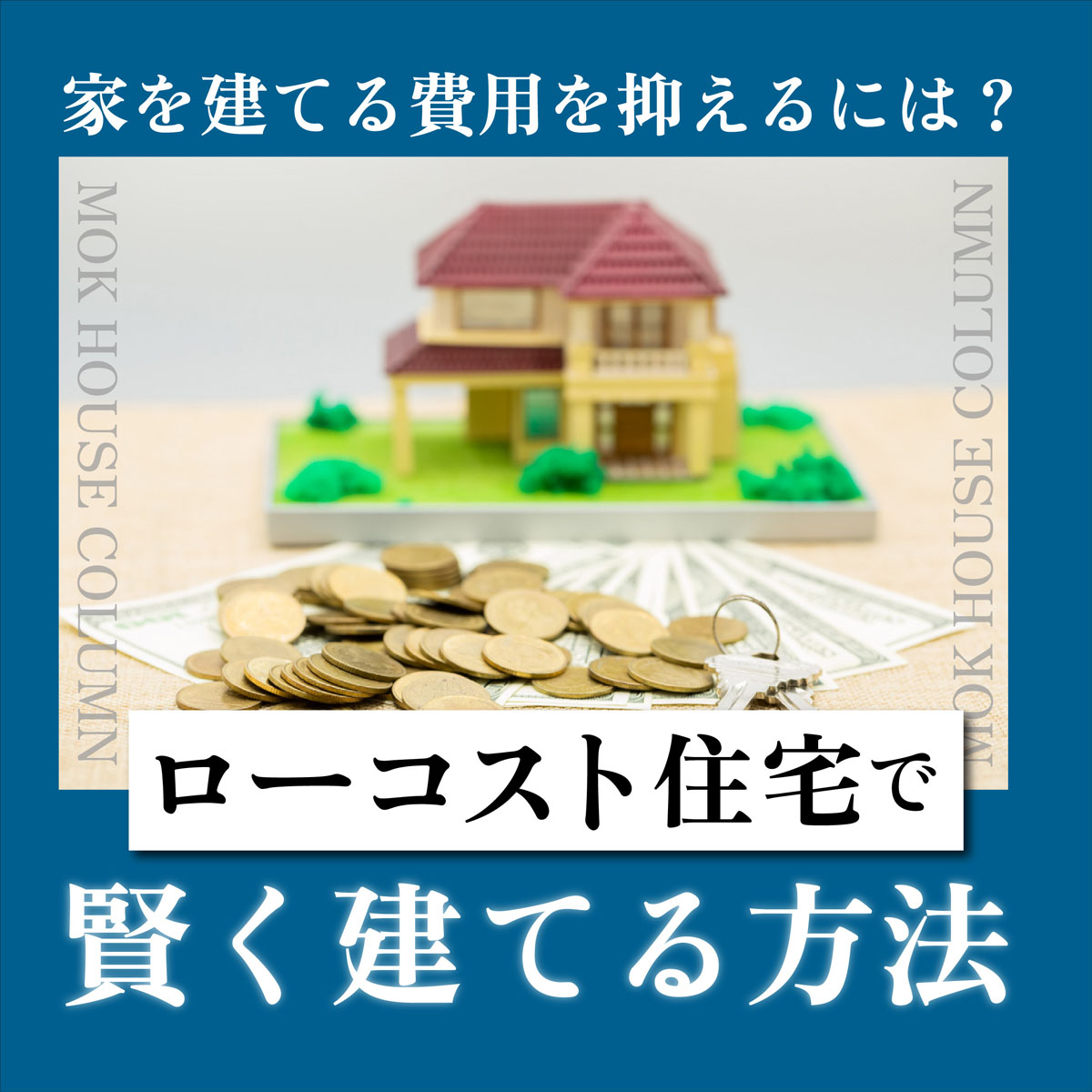
家を建てる費用を抑えるには 「ローコスト住宅を賢く選ぶこと」 がカギ
「家を建てたい」と考え始めたとき、まず心配になるのはやっぱりお金のことではないでしょうか。頭の中で“いくらぐらい必要なんだろう?”と計算を始めて、思わずため息をついた経験がある人も多いと思います。
実際に家を建てた友人は「最初の見積もりよりも数百万円高くなった」と振り返っていました。
本体工事だけでは済まず、土地代や外構工事、登記や税金など細かい費用が次々に出てきたからだそうです。これを聞いたとき、「やっぱり家づくりは思った以上にお金が動くんだ」と実感しました。
だからこそ、最初の段階で“総額でどのくらいかかるのか”をイメージしておくことが大事 です。ぼんやりとした数字のまま進めると、後で「こんなはずじゃなかった」となりかねません。
安心して計画を立てるには、まず現実的なラインを知ることから始める必要があります。
埼玉・千葉・東京でローコスト住宅を建てたい方は、ポラスグループ(対応エリア:埼玉・千葉・東京)のモクハウスにご相談ください。
柏と船橋の「体感すまいパーク」では注文住宅5ブランドのモデルハウスを見比べることができ、新座や春日部のショールームでも、土地探しからプラン検討まで専門スタッフがサポートします。

家の費用はどのくらい?相場とローコスト住宅の違い

「家って結局いくらかかるの?」──家づくりを考え始めたときに、誰もが気になる疑問です。
建物そのものの価格だけを思い浮かべる人が多いのですが、実際には地盤改良や外構工事、登記、税金など細かい費用もついてきます。
こうしたものを足していくと「想像していたより高かった」と感じる人が少なくありません。
全国的な目安を見てみると、ざっくり3,000万〜5,000万円あたりが相場だと言われます。
都市部では土地代がとても大きく、同じ30坪の家でも5,000万円近くかかるケースがあります。「希望のエリアにこだわったら、思った以上に金額が膨らんだ」という話もよく耳にします。
逆に郊外や地方であれば、土地代を抑えられるので総額が3,000万円台に収まることもあり、住む場所による差は非常に大きいのです。
そこで注目されるのが「ローコスト住宅」 です。

坪単価で30万〜50万円程度が目安とされ、30坪なら1,800万円前後で建てられるケースもあります。
「そんなに抑えられるの?」と驚くかもしれませんが、理由は単純。
間取りや屋根形状をすっきりさせて施工を効率化し、人気設備を標準仕様にまとめて大量発注するなど、余分なコストを徹底的に削っている
からです。
「安さ=品質が低い」と考える人もいますが、日本で建てられる住宅は建築基準法に沿って設計されるため、安全性や耐震性はしっかり守られています。
むしろ、ローコスト住宅は「派手さを省いて必要な性能に集中した家」と表現した方が近いでしょう。
結局のところ、家の費用は「どこに建てるか」と「どんな住まいを選ぶか」で大きく変わります。大切なのは、自分たちの暮らし方に本当に合うレベルを見極める ことです。
家の費用を下げる工夫とは?
「なるべく費用を抑えて建てたい」──多くの人がそう考えると思います。でも、ただ削るだけでは後悔につながります。そこで大切なのは、暮らしやすさを維持しつつムダをなくす工夫です。
シンプルな間取りにする

凸凹の多い間取りや凝ったデザインは、その分手間と材料が増えてコストアップにつながります。
逆に、四角い箱型の家は施工効率がよく、壁や屋根の面積も少なく済むので費用を抑えやすいんです。たとえばリビングの近くに水回りをまとめただけで、「家事の移動がラクになったうえにコストも下げられた」という実例もあります。
設備や仕様は“必要十分”を選ぶ
グレードを上げればキッチンやお風呂も豪華になりますが、金額も一気に跳ね上がります。「実際に暮らしてみたら、標準仕様で十分だった」という声はとても多いです。ローコスト住宅では人気の設備を標準にまとめて発注しているので、うまく選べば無駄なく快適に暮らせます。
外観デザインはほどほどに
屋根の形や外壁の素材は見た目の印象を左右しますが、複雑にすればその分高額に。シンプルな切妻屋根やサイディング外壁を選んだ人の多くが「掃除もしやすくて助かる」と話しています。外観はおしゃれにしつつも“やりすぎない”のがポイントです。
会社やプランを比べて選ぶ

同じ30坪でも、会社によって数百万円の差が出ることがあります。規格住宅やキャンペーンプランを使えばコストダウンしやすく、「見積もりを複数とってよかった」と実感する人も少なくありません。
DIYで手を加える
最近では、外構や収納を自分で仕上げる人も増えています。
休日に家族で棚をつくったり、庭を整えたりするだけでも数十万円の節約につながることがあります。「自分の手で完成させた部分があると、家への愛着も増した」という声も多いのです。
結局、家の費用を抑える秘訣は「何を優先し、何を割り切るか」を決めることです。安さを追い求めるのではなく、“必要なところにお金をかけて、その他はシンプルにする” 。この考え方がローコスト住宅の本質であり、後悔しない家づくりのコツになります。
ローコスト住宅のメリットとデメリットは?
「ローコスト住宅って、本当に大丈夫なの?」──費用を抑えたいと考えながらも、心のどこかで不安を抱える人は多いと思います。ここでは、実際に感じやすい良い点と注意点を整理してみましょう。
メリット:生活に余裕が生まれる

一番大きいのは、やはり家計への負担が軽くなることです。
ローコスト住宅では間取りや設備を標準化しているため、1,500万〜2,000万円台に収められるケースも少なくありません。ローンの返済が抑えられることで「教育費や貯金に回せる余裕が出た」と話す家庭もあります。
また、シンプルな設計は毎日の暮らしにも直結します。
部屋数を増やしすぎない間取りは掃除がしやすく、動線も短くて家事がスムーズ。「必要なものだけを選んだら、思った以上に快適だった」という声もよく聞かれます。見た目の豪華さより実用性を優先したい人にとって、ローコスト住宅は現実的で賢い選択肢になります。
デメリット:自由度に限界がある

一方で、注意しておきたいこともあります。
標準仕様から外れてオプションを多く追加すると、結局は高額になり「ローコスト」とは言えなくなるケースがあります。
また、「もっとデザインにこだわりたかった」「やっぱり広いキッチンにすればよかった」と、後から思う人も少なくありません。外観や内装を豪華にしたい人にとっては、物足りなさを感じる場面が出てくるでしょう。
後悔しないためのチェックポイント
ローコスト住宅を検討するなら、次の点を事前に確認しておくと安心です。
・耐震性や断熱性など、基本性能は十分か
・標準仕様で満足できそうか、それともオプション追加が前提になりそうか
・将来の修繕やメンテナンス費用を見越せるか
実際に建てた人の声でも、「最初に優先順位を整理していたから満足できた」という意見が多いです。
逆に、考えずに契約を進めてしまうと「後でオプション費用がかさんだ」と後悔することも。
大事なのは「今の暮らしに本当に必要なもの」
を冷静に選び抜くことです。
家の費用を抑える土地選びのポイントって?

「ローコスト住宅を建てよう」と思っても、土地の費用が高ければ全体の予算は膨らみます。
実際、建物代をうまく抑えたのに「土地にお金を使いすぎてしまった」という話もよく耳にします。家の費用を本当に下げたいなら、土地の条件を見極めることが欠かせません。
整形地と変形地の違い
四角い整形地は建築効率が良く、シンプルな間取りを組みやすいのでコストを抑えるうえで有利です。
一方で、旗竿地や三角形の土地などは価格が安めに見えても要注意。
造成工事や特殊な設計が必要になり、結果的に費用が上がってしまうことがあります。実際に「安いと思って契約したのに、外構や造成で数百万円かかった」というケースもあります。
インフラ整備の有無
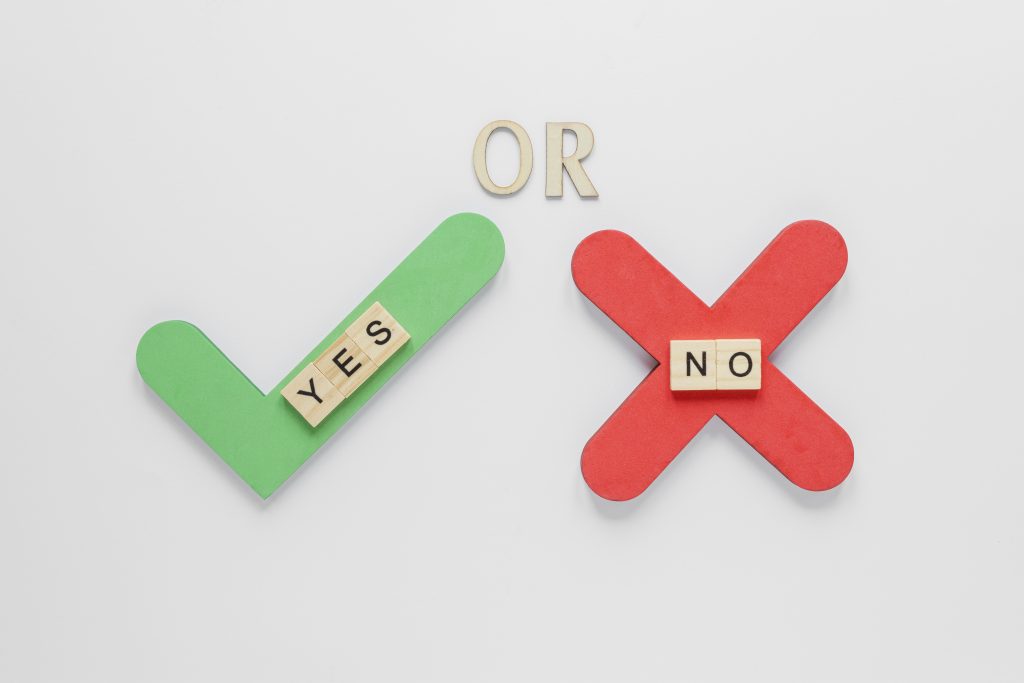
上下水道や電気、ガスの引き込みが整っているかどうかも大きなポイントです。インフラが未整備の土地は一見お得に見えても、工事費が追加で発生して数十万〜数百万円の出費につながることも。
知人の中には「土地自体は割安だったけれど、引き込み工事で思ったより高くついた」と話していた人もいます。
ローコスト住宅のメリットを活かすには、こうした見えない費用もあらかじめ計算に入れておくことが大切です。
通勤・通学とのバランス

郊外の土地は価格が安く、魅力的に映ります。
ただし、通勤や通学にかかる交通費や時間を考えると「毎月の負担は結局同じだった」ということもあります。
たとえば、電車代やガソリン代が家計にのしかかると、数年で数十万円以上の差になることも。土地選びでは「毎日の生活コスト」まで視野に入れることが必要です。
将来の資産価値
土地は住むだけでなく、将来的には売却や相続の対象になる資産でもあります。
条件の悪い土地を選ぶと、将来「売りたくても売れない」という事態になりかねません。
逆に、インフラ整備や地域の発展計画がある場所は、資産価値が維持されやすい傾向にあります。費用を抑えたいからといって安さだけで判断せず、先を見据えて選ぶことが大事です。
ローコスト住宅は安全性や耐久性で不安はない?

「安い家だと強度や寿命が心配…」と感じる人は少なくありません。ローコスト住宅という言葉から「安かろう悪かろう」を連想してしまうのも自然なことだと思います。でも、実際のところはどうなのでしょうか。
建築基準法が守ってくれる安心感
日本で建てられる家は、必ず建築基準法に沿って設計されます。
耐震基準や防火基準を満たさなければ許可が下りないため、ローコスト住宅でも最低限の安全性はきちんと担保されています。ある方は「担当者から“法律で決まっている基準は全部クリアしていますよ”と説明されて、ようやく不安が和らいだ」と話していました。
工夫で費用を抑えている

「安い=材料が粗悪」というイメージを持つ人もいますが、ローコスト住宅の特徴はそこではありません。
屋根や外壁をシンプルにしたり、建材をまとめて仕入れたりして、効率化によって費用を抑えているのです。つまり、性能を削っているのではなく“ムダを減らしている”のが実態です。
耐久性とメンテナンス
長く暮らす上で大事なのは耐久性です。
ローコスト住宅でも基本的な性能は備わっていますが、外壁や屋根がシンプルなぶん、定期的なメンテナンスを意識しておく必要があります。
10年ごとの外壁塗装や20年ごとの屋根の補修など、あらかじめ修繕計画を立てておけば安心です。
実際に「建てた当初は心配だったけど、計画的にメンテナンスしていたら不安はなかった」という声も聞かれます。
性能を数値で確かめる方法

不安を減らすために「住宅性能評価」を確認するのも一つの手です。
耐震や断熱、劣化対策といった等級が数字で示されるので、「費用は抑えたけど性能はしっかりしている」と自信を持てます。数字で裏付けされると納得しやすく、検討時の安心材料になりますよね。
調査データから見る家の費用とローコスト住宅の現状
家を建てるときに「結局どのくらいのお金が必要なの?」と迷う人は多いはずです。
そんなときに役立つのが、公的な調査データです。数字を知ることで「やっぱりこれくらいかかるんだ」と納得できたり、「思ったより高い!」と驚いたり、自分の計画を見直すきっかけにもなります。
■国の調査に見る平均額

国土交通省が発表した住宅市場動向調査(令和6年度)によると、注文住宅(土地代込み)の平均はおよそ6,200万円という数字が出ています。
「そんなにするの?」と感じる方もいるかもしれません。実際に土地代の高い都市部では、この金額に近い事例が多く、住宅展示場で「予算オーバーになってしまった」と話す人も珍しくありません。
■ローン利用者の傾向
一方で、住宅金融支援機構がまとめた「フラット35利用者調査(2024年版)」では、建築費を2,000万〜2,500万円に抑える世帯が一定数いることもわかっています。
共働き家庭が増え、教育費や老後資金を意識する人が多い中、「無理のない範囲で家を持ちたい」という現実的な姿勢が反映されていると言えるでしょう。知人の中にも「背伸びしなかったから余裕を持って暮らせている」と話す方がいます。
■性能基準と安心感

最近は「安く建てても安心できるのか」が大きな関心ごとです。
そこで役立つのが住宅性能表示制度。
耐震性や断熱性などを等級で確認できる仕組みで、ローコスト住宅でもこの制度に沿って建てられている場合があります。
「数字で性能が見えるから不安が減った」と話す購入者もいて、費用を抑えたい人にとって安心材料になっています。
■データが示す変化
これらの調査から見えてくるのは、「費用を抑えた家づくり」が特別ではなくなってきているという現実です。
以前は「安い家=質が悪い」というイメージも強かったですが、今は「自分の暮らしに合った範囲で建てる」という考え方が広がっています。数字の裏側には、堅実に暮らしを考える人たちの姿勢が反映されているのです。
実際の暮らしから学ぶローコスト住宅の家づくり事例
数字や制度の説明だけでは、ローコスト住宅の魅力はなかなか実感できません。ここでは、実際に家を建てた人たちのエピソードをいくつか紹介します。
■共働き夫婦が選んだシンプルな住まい

30代の共働き夫婦は、子どもが生まれたのをきっかけに家づくりを決めました。予算はできるだけ抑えたい。でも子育てのしやすさは譲れない。
そこで選んだのは、延床30坪・3LDKのローコスト住宅でした。リビングを中心に水回りをまとめ、外観は四角い箱型でシンプルに。結果、建築費は2,000万円以内に収まり、ローンの負担も軽くなり「子育てに安心して向き合える環境が整った」と話していました。
■“必要なものだけ”に絞った選択
別の家庭では、豪華な設備に惹かれつつも「実際に使うかどうか」を徹底的に考えました。
アイランドキッチンや大型の浴室乾燥機は外し、その分を断熱性能や収納にまわす形に。住んでから「欲しかった機能はきちんと備わっていて、無駄な出費がなかった」と満足感を口にしています。
■若いうちに建てた20代夫婦の例
20代前半の夫婦は「賃貸にお金を払い続けるより、早めに自分の家を」と考えてローコスト住宅を選びました。
建築費を抑えたことで、月々のローン返済額は家賃とほぼ同じ。しかも新築に住める安心感があり、「若いうちに決断してよかった」と実感しています。
■二世帯住宅をローコストで実現

親世帯と同居を考えたある家庭は、費用が膨らむのを心配していました。
そこでローコスト住宅をベースに、1階と2階で世帯を分けるシンプルな二世帯住宅を計画。建築費は大幅に抑えられ、それぞれの世帯が快適に暮らせる住まいを実現しました。
これらの事例に共通しているのは、「費用を抑える=妥協」ではないということです。むしろ優先順位を整理したからこそ、満足度の高い家づくりができたという声が多いのです。
ローコスト住宅は“現実的に暮らしを整える手段” として、多くの家族に選ばれているといえるでしょう。
家と費用、ローコスト住宅に関するよくある質問
Q. ローコスト住宅でも自由設計できますか?

「ゼロから全部決めたい!」となると難しいですが、規格プランをベースに間取りを少し変えたり、オプションを追加したりはできます。
実際に建てた人も「完全自由じゃなかったけど、暮らしに合う形にはできた」と話していました。
Q. 安く建てると、後から修繕費が高くつきませんか?
そう思う方は多いですね。大事なのは基本性能がどうか。
耐震や断熱を押さえておけば、無駄な修繕に悩まされにくいです。「光熱費まで考えて選んでよかった」と言っていた方もいます。
Q. 保証やアフターは心配ない?

これはよく聞かれます。ローコスト住宅でも法律で10年保証は必須ですし、会社によっては定期点検や延長保証もあります。契約前に「どこまで対応してくれるか」を確認しておくと安心ですよ。
Q. 中古と比べるとどっちがお得?
「中古を買ってリフォームの方が安いのでは?」と考える人もいます。確かに価格は下がりますが、リフォームで数百万円かかることも。新築のローコスト住宅なら最初から最新基準を満たしていて、安心して長く住めるのが強みです。
Q. 何年くらい住めますか?
「安い家は短命なんじゃ?」とよく言われますが、きちんとメンテナンスすれば30〜40年は十分に暮らせます。知人も「思った以上に長持ちしている」と笑っていました。
Q. 太陽光や省エネ設備は追加できます?

もちろん可能です。太陽光パネルや断熱窓は追加費用がかかりますが、光熱費の削減や補助金で元が取れるケースもあります。実際に導入した家庭では「光熱費が減って助かった」と喜んでいました。
Q. 建売と注文のローコスト住宅、どっちがいい?
すぐに住みたい人には建売、間取りを少し調整したいなら注文。そんなふうに選んでいる人が多いです。どちらも一長一短なので、生活スタイルに合わせて考えるのが一番ですね。
まとめ|家の費用を抑えるにはローコスト住宅をどう選ぶか
家を建てるとき、誰もが直面するのは「限られた予算の中で、どこまで理想に近づけるか」という課題です。土地代や諸費用を含めれば、想像以上に大きな金額になります。

そのなかでローコスト住宅は「必要な性能は守りながら、無駄を減らす」という現実的な選択肢として注目されています。
ローコスト住宅が実現できるのは、間取りをシンプルにしたり、設備を標準化したりといった工夫の積み重ねです。
派手な部分をそぎ落とす代わりに、耐震性や断熱性といった暮らしに直結する性能はきちんと確保されています。つまり「安いから不安」ではなく「合理的に選んだ結果」ととらえる方が自然でしょう。
もちろん、安さだけを追えば後悔につながることもあります。修繕費や光熱費、土地条件なども含めてトータルで考えることが大切です。
結局のところ、家づくりのカギは「何を優先し、どこを割り切るか」を整理することにあります。
「費用を抑える=妥協」ではなく、「家族の暮らしに合った選択をすること」。
その考え方が、後悔のない家づくりにつながるのだと思います。
埼玉・千葉・東京でローコスト住宅を検討している方は、ポラスグループの「モクハウス」にぜひ相談してみてください。