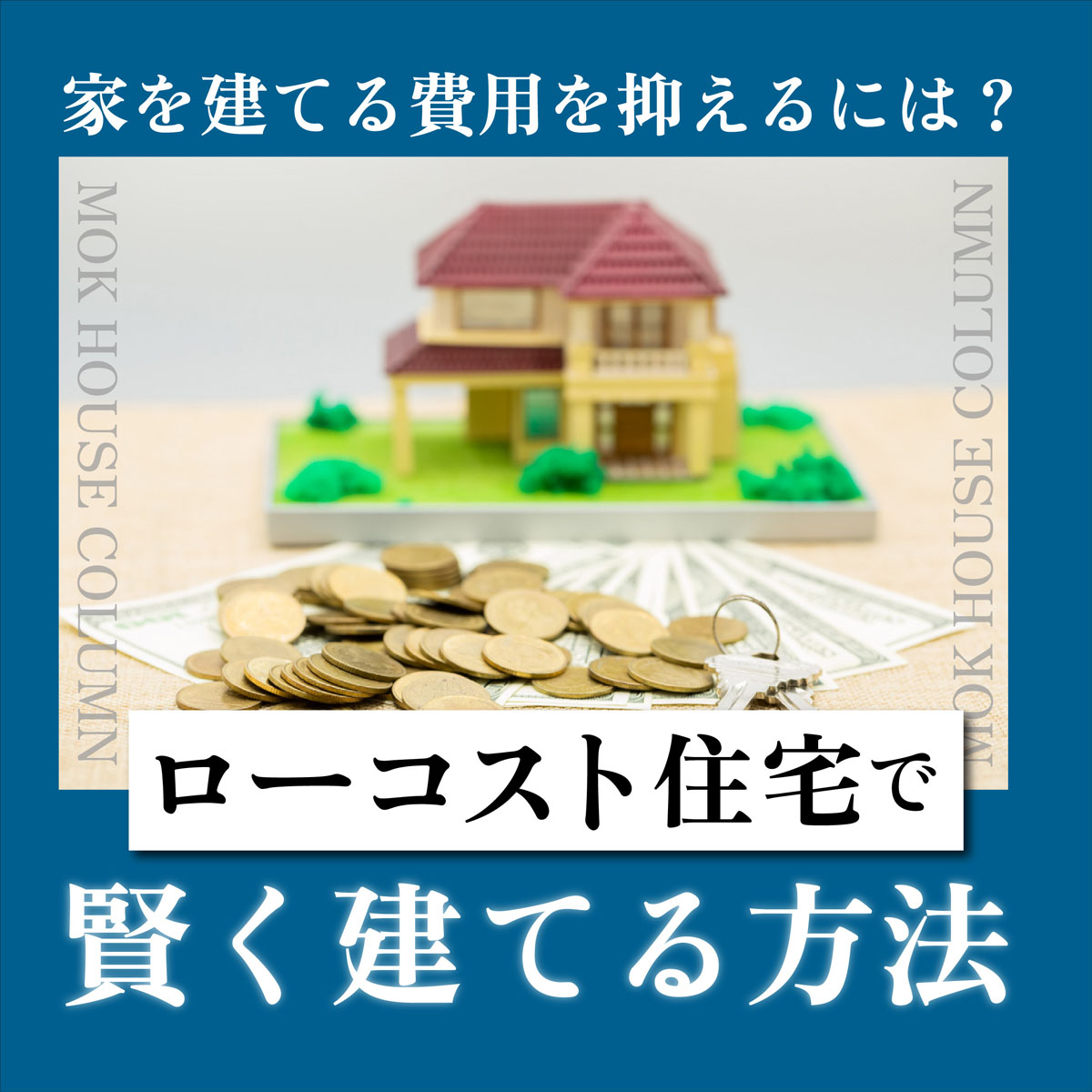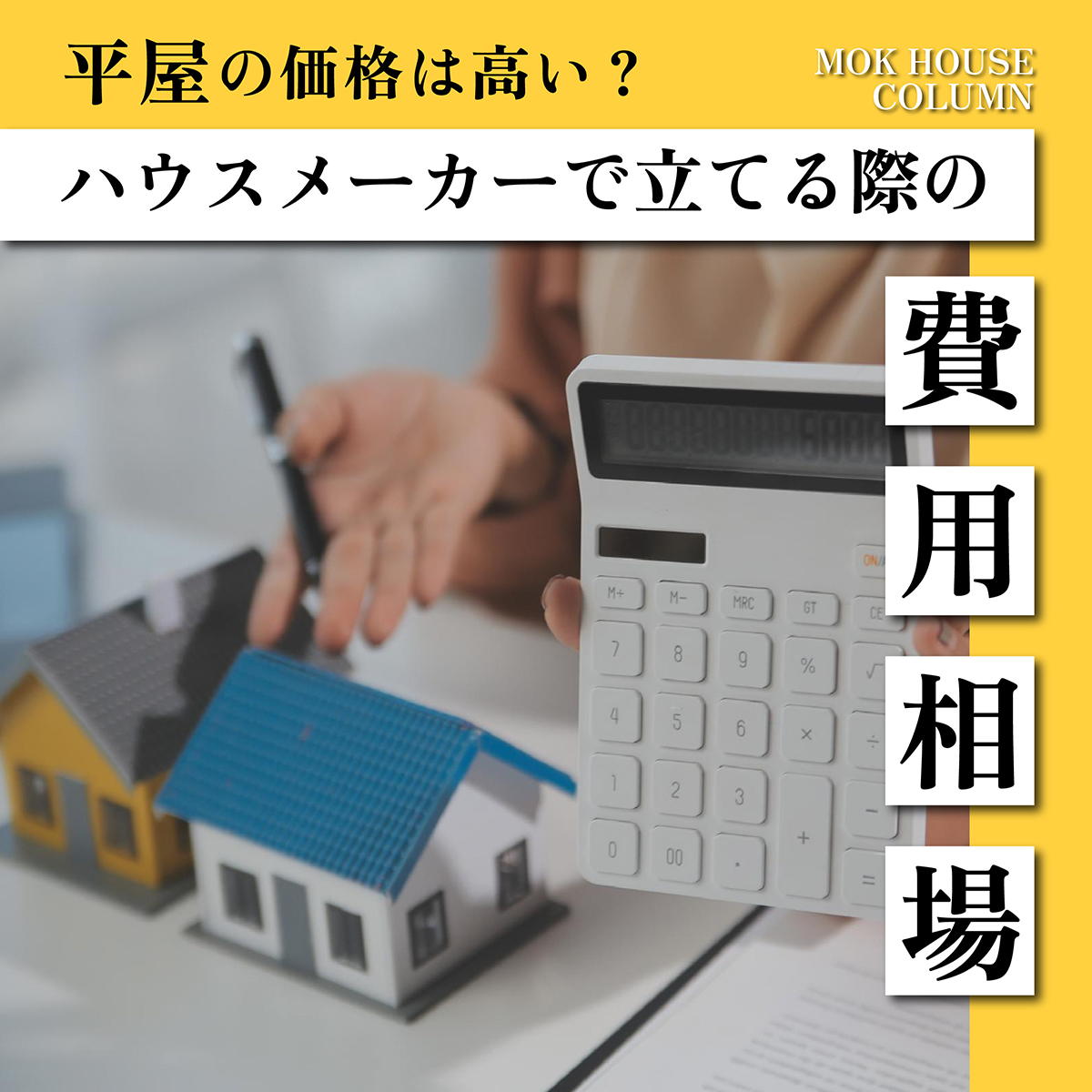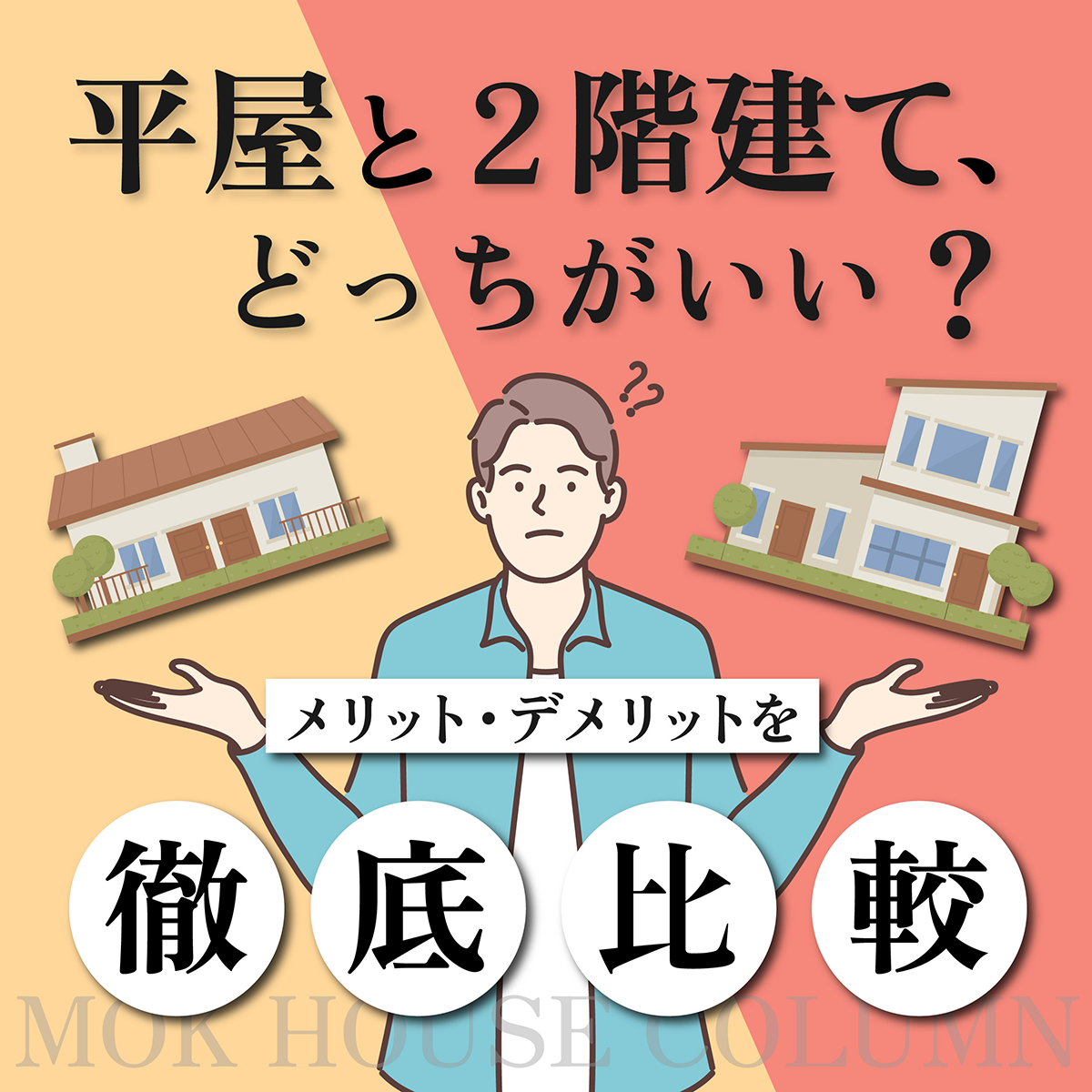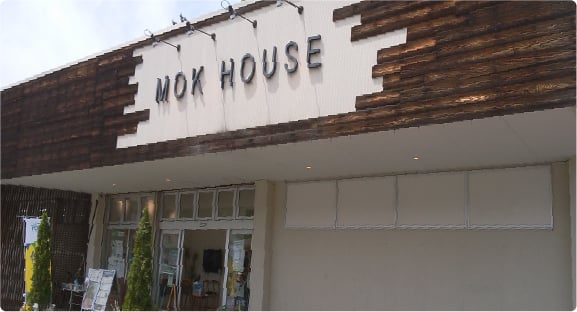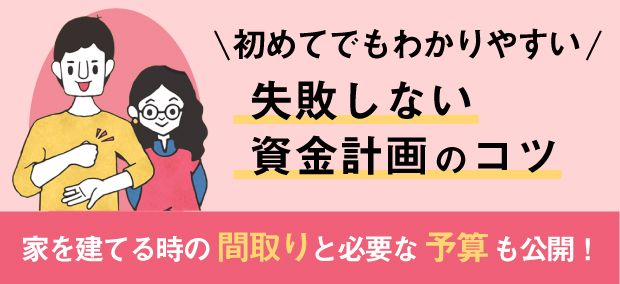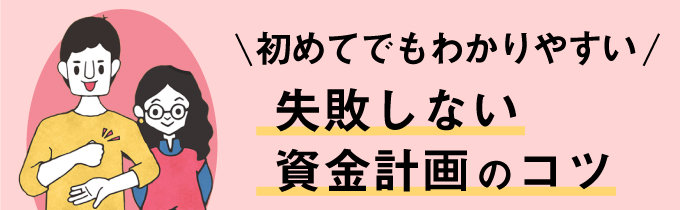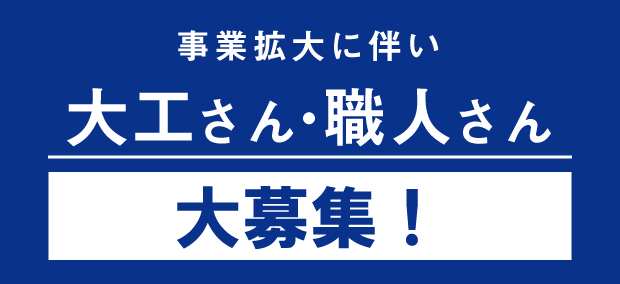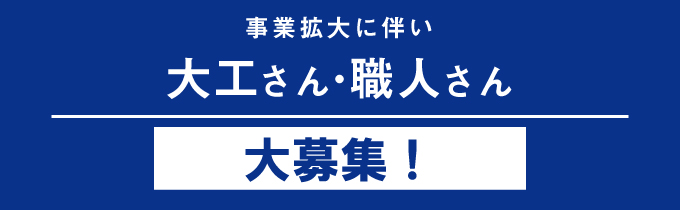家を安く建てるための方法は?費用を抑える5つのポイント
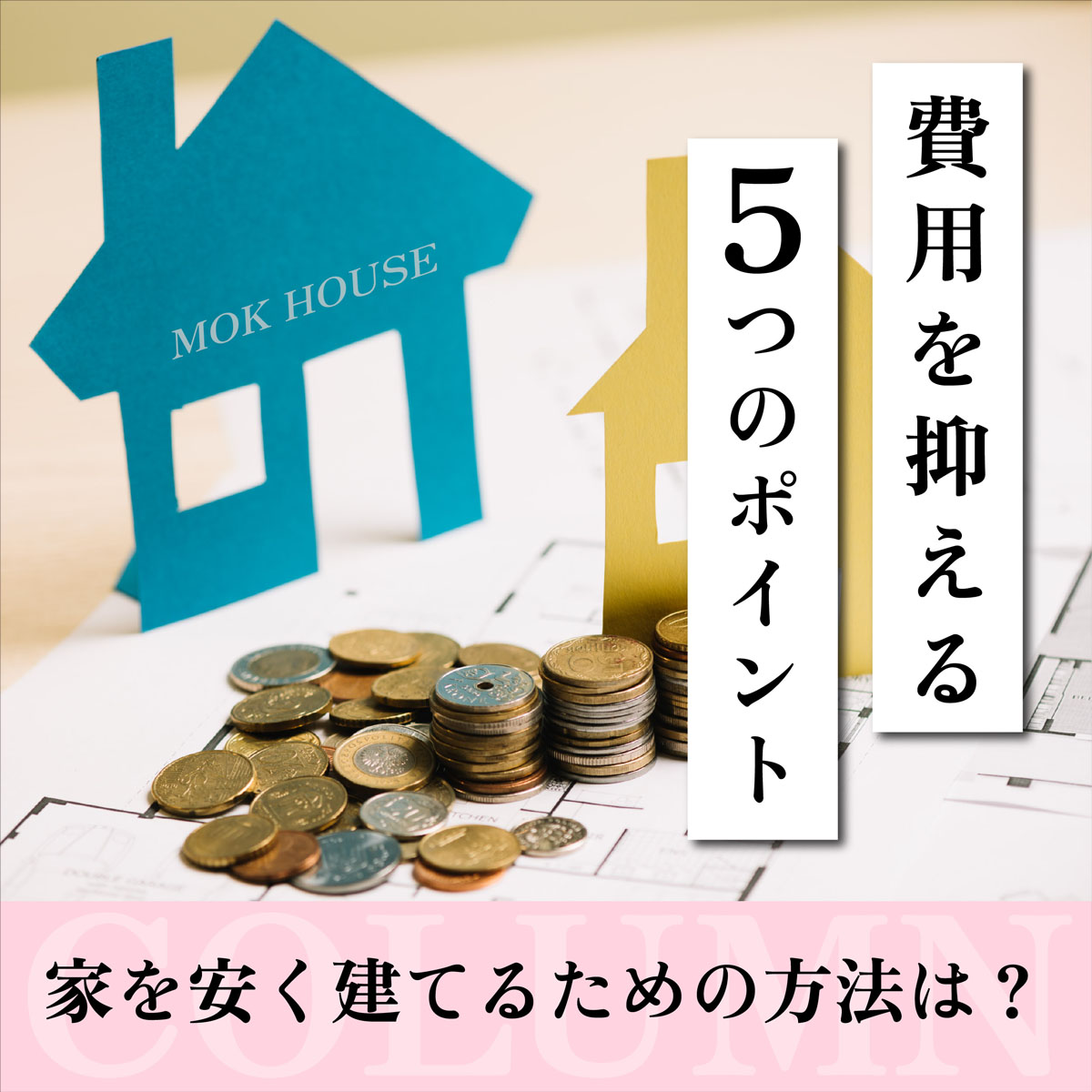
結論から言うと「家を安く建てる方法は5つの工夫に集約されます」
「家を建てたいけど、やっぱり高いよな……」とため息をついたこと、誰にでもあるのではないでしょうか。
でも、少し視点を変えるだけで、家づくりの費用は思いのほか違ってきます。
ポイントは、建てる時期・間取りのシンプル化・金融制度の使い方・土地条件・将来コストの見通し
。
この5つを意識するだけで、「安く建てたのに住み心地がいい家」が現実します。
つまり、“安く建てる”とは、材料を削ることではなく、暮らしの優先順位を整理すること。
無理をしない工夫こそが、家づくりの満足度を高めてくれると思います。
このコラムでは、実際に費用を抑えるための具体的な工夫を紹介します。
「なるほど、これならできそう」と感じてもらえるヒントを、いくつか拾っていきましょう。
埼玉・千葉・東京でローコスト住宅を建てるなら、ポラスグループ(対応エリア:埼玉・千葉・東京) のモクハウスにご相談ください。
柏と船橋にある、ポラスグループ(対応エリア:埼玉・千葉・東京) の注文住宅5ブランドのモデルハウスが見られる「体感すまいパーク」、また新座と春日部にあるショールームで、皆様のご来場をお待ちしております。

家を安く建てるための費用を抑える5つのポイント
家を安く建てるには?工事時期や契約タイミングで費用は変わる?
■時期をずらすだけで費用が変わる理由

同じ間取りでも、“いつ契約するか”で費用が変わる
。実はこの差、思った以上に大きいのです。
住宅会社には繁忙期と閑散期があり、職人や資材の動き次第で見積もりが上下します。
たとえば春や秋は新生活シーズンで契約が集中。 この時期は値引き交渉が難しくなることも多いです。
一方、夏や冬は比較的落ち着いていて、会社も契約を増やしたいタイミング。
この時期にはキャンペーンや特典が出やすく、同じプランでも100万円前後の費用の差が出ることも。
冬に契約したご夫婦が「こんなに違うとは思わなかった」と驚いていた、という話もあります。
担当者いわく「閑散期は職人の予定が組みやすく、見積もりに柔軟さが出る」そうです。
こうした“業界の季節感”
を少し知っておくだけでも、家づくりは有利に進められます。
■決算期や補助金制度も“チャンスの時期”

決算期や年度末は、会社が数字をまとめたい時期。
このタイミングには「今月中の契約で○○万円値引き」といった特典もよく見られます。
「数棟限定キャンペーン」と案内されるケースも多く、見逃せません。
さらに、国や自治体の補助金制度もタイミング勝負です。
制度は年度ごとに条件が変わり、数か月で締め切られることも。 「知っていれば使えたのに」と後悔する人も少なくありません。
展示場や自治体サイトを定期的にチェックしておく。それだけでも、結果的に数十万円の費用節約につながることがあります。
■“いつ建てるか”で家づくりは変わる
安く建てたいなら、仕様や設計だけでなく「契約のタイミングを読む力」も必要です。
焦らず、季節や制度の流れを見ながら動く。
その意識があるかないかで、最終的な費用は驚くほど変わります。
無理をせず、慌てず、タイミングを選ぶ。それが、“賢く安く建てる”ための第一歩です。
家を安く建てるには?間取りや設計をどう工夫すべき?
■シンプルな形が“安くて強い”家をつくる
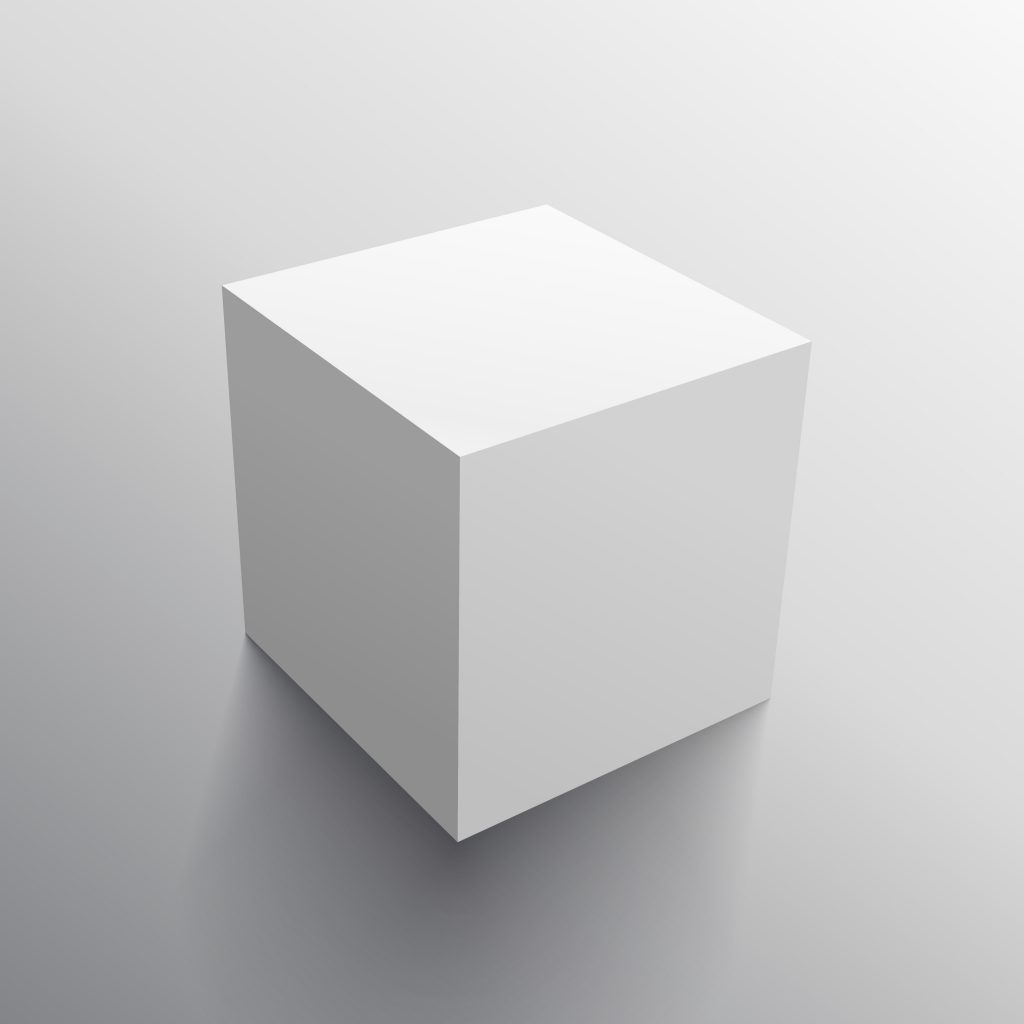
家づくりで費用を抑えたいなら、まず意識したいのが形のシンプルさです。
外観に個性を出したい気持ちは自然ですが、凹凸が多い家ほど材料や手間が増え、結果的にコストが上がります。
屋根や外壁が入り組むと足場や工期も長くなり、職人の作業費にも影響します。
一方、四角い箱型の家は構造が安定し、工事もスムーズ。
シンプルでも素材やライン次第で十分おしゃれに仕上がります。
「形を整えたら予算も掃除の手間も減った」という声も多く、ムダのない家ほど強く長持ちするといえます。
■水回りをまとめると、費用も動線もスッキリ

次に見直したいのが水回りです。
キッチン・洗面・浴室を近くにまとめると、配管が短くなり工事費を抑えられます。
「料理→洗濯→お風呂」の動線が一直線になるだけで、家事がぐっと楽になります。
見た目よりも機能性を意識すると、自然とコストダウンにつながります。
“見えない部分”ほど、費用にも暮らしやすさにも直結するポイントです。
■将来を見据えた設計が“長く安く暮らせる家”をつくる
家は建てて終わりではありません。
10年、20年と暮らす中で、出費をどれだけ抑えられるかが大切です。
たとえば子ども部屋を最初から仕切らず広めにしておけば、成長に合わせて家具で区切れます。
また、1階で生活が完結する間取りにすれば、将来のバリアフリー改修費も不要です。
“今の節約”より“あとで困らない設計”を意識することが、結果的に賢い選択になります。
■削るより“整える”が節約の近道
家づくりの「安さ」は、我慢ではなく暮らしに合わせて整えること。
必要な場所にだけお金をかけ、シンプルにまとめる。それが、“安くて心地よい家”をつくる一番の近道です。
家を安く建てるために使える金融制度やローンの工夫
■金利ひとつで、家の総額は思った以上に変わる

家づくりで意外と見落とされがちなのが 「お金の借り方」です。
建物代ばかりに目が行きがちですが、実際はローンの金利や返し方で総額が大きく変わります。
たとえば金利が0.3%違うだけで、35年ローンなら100万円以上の差になることもあります。
最近はネット銀行を選ぶ人も多く、手数料を抑えたり繰上げ返済がしやすかったりとメリットが豊富です。
一方で、地元の金融機関には「相談しやすい安心感」があるのも確か。
どちらが正解というより、自分たちが納得できるかどうかが大事です。
また、長期固定金利の「フラット35」は金利が一定なので、将来の家計を見通しやすいのが特徴です。
“安く借りる”よりも、“無理なく続けられる”ほうが、結果的に安心につながります。
■控除や補助金制度は“知っている人”が得をする

住宅ローン控除は、毎年の年末残高に応じて税金が戻る制度です。
10年〜13年間、減税を受けられるので長期的には大きな助けになります。
さらに国や自治体の補助制度。
たとえば「子育てエコホーム支援事業」や「ZEH支援金」など――を活用すれば、100万円近い支援を受けられる場合もあります。
手続きはやや面倒に感じますが、住宅会社が代行してくれるケースも多く、「思ったより簡単だった」という声も少なくありません。
制度を知っているかどうかで、結果がまるで違ってきます。
“情報を持っている人が得をする”のは、家づくりの世界でも同じです。
■コツコツの繰上げ返済が、未来の安心につながる

ローンを組んだ後も、返し方の工夫で支払総額を減らせます。
たとえば、年に10万円ずつでも繰上げ返済を続けると、利息を数十万円単位でカットできることも。
「余裕のあるときに少し返す」を積み重ねるだけでも、将来のゆとりが変わります。 教育費や老後資金とのバランスを見ながら、自分たちのペースで進めれば十分です。
焦らず、無理せず、返済をコントロールする。
それもまた、“家を安く建てる”ための大切な視点です。
■“借り方”を整えることも、家づくりの一部
家を安く建てるというのは、建物の話だけではありません。
どう借りて、どう返すか――お金の設計も家づくりの一部です。
低金利のローンを選び、控除や補助金を活用する。
この3つを意識するだけでも、支払い総額はぐっと抑えられます。
同じ家でも借り方次第で未来の暮らしが変わる。
“お金の間取り”を整えることが、長く安心して暮らせる家への近道です。金利や制度は、知るか知らないかで本当に違ってきます。一度、身近な金融機関にも話を聞いてみると新しい発見があると思います。
家の費用を左右する土地選び|どんな条件を選べば安く建てられる?
■形と地盤で“建てやすさ”は大きく変わる

家の費用は建物だけでなく、土地の条件でも驚くほど変わります。
同じ30坪でも、形や地盤の違いで工事費がまったく異なることがあります。
まず注目したいのは、整形地と変形地の違い。
四角い整形地は設計しやすく、基礎もシンプルでコストを抑えやすいです。
一方、三角地や旗竿地は一見安く見えても、造成や配管工事が必要になり、結果的に費用がかさむことがあります。
地盤が弱い土地では地盤改良が必要になり、追加で数十万円〜百万円かかることも。
購入前に地盤調査の有無を確認しておくと安心です。「安い土地=お得」とは限らない
というのが現実です。
■インフラと生活コストの“見えない差”に注意

土地代だけで判断すると、思わぬ出費が発生することがあります。
上下水道や電気、ガスが未整備だと引き込み工事が必要で、数十万円単位の費用差が出るケースも。
さらに、通勤や買い物の交通費も意外に大きな要素です。
郊外の土地は価格が安くても車移動が増え、ガソリン代がかさむ場合があります。
反対に駅近や生活施設の整った土地なら、日々の出費を抑えやすいです。
土地の値段だけでなく、「暮らしてからのコスト」まで含めて見るのがポイントです。
■トータルで見ると“高く見えて安い土地”もある

整備済みの土地は少し高く見えても、造成やインフラ工事が不要な分、結果的に安くなることがあります。
逆に安い旗竿地を買って通路や照明を整備し、結果的に割高になる例もあります。
初期費用よりも、生活を始めてからのコストを意識して選ぶ。
数字では見えない部分に、実は大きな差が生まれます。
■土地と建物をセットで考える
家の費用を抑えるには、土地と建物を一体で考えることが重要です。
・整形地を選んで設計をシンプルに
・インフラの有無を確認して余計な出費を防ぐ
・生活コストも含めてトータルで判断する
土地選びは“買う”というより、“長く暮らすための投資”です。
焦らず比べて、自分たちの暮らし方に合う場所を選ぶことが、安くて満足できる家への近道です。
安く建てる家ほど後の費用が心配?トータルコストで考える家づくりのコツ
■初期費用だけで判断すると、後で損をすることも

「できるだけ安く建てたい」と思うのは自然なこと。
ただ、初期費用だけで判断すると、あとから出費がかさむケースもあります。
たとえば断熱性能の低い家では、冬の暖房費や夏の冷房費が高くなりやすい。
外壁や屋根のグレードを落とすと、10年以内に再塗装や修繕が必要になる場合もあります。
最初は安くても、維持費が増えれば結果的に負担は大きくなります。
“安く建てる”とは、建てたあとも安く暮らせる家にすること。
短期のコストだけでなく、長期のバランスを意識するのが大切です。
■省エネ設備は“支出を減らす投資”

初期費用が少し上がっても、省エネ設備は長期的に見ればプラスになります。
断熱材や高性能サッシを使えば冷暖房効率が上がり、光熱費を抑えられます。
太陽光発電や蓄電池を組み合わせれば、10年前後で導入費を回収できることも。
「家は投資」と考えれば、先にかけるお金が後の節約につながると実感できるでしょう。
■素材の選び方でメンテナンス費が変わる

維持費を抑えるなら、耐久性の高い素材選びもポイントです。
ガルバリウム鋼板や高品質サイディングは再塗装の間隔が長く、補修コストを抑えやすい。
屋根材も軽量タイプを選べば、地震時の負担が小さく、修繕費も低くなります。
“長くもつ素材を選ぶ”ことが、結果的にトータルでの節約につながります。
■“建てるとき”と“暮らすとき”の両方を見据える
本当に安く建てるとは、建築費だけを下げることではありません。
光熱費・修繕費・維持費といった暮らしのコストを含めて考えることが大切です。
・省エネ性能と耐久性を重視する
・設備や素材を“将来の節約”ととらえる
・維持費も含めて全体コストで判断する
この3つを意識すれば、「安く建てて安く暮らす」家づくりが現実になります。家を建てるとき、つい初期費用ばかり見てしまいますよね。
でも、10年後を想像すると選び方も変わる気がしませんか?
家づくりの費用、実際どれくらい?最新データで確認
■家づくりは“感覚”ではなくデータで考える
家の価格は「4,000万円くらいかな」といった感覚で語られがちですが、実際は地域や条件で大きく異なります。
思い込みで予算を立てると、計画の見直しや資金不足につながることも。
データを一度整理しておくと、現実的な判断がしやすくなります。ここでは最新の調査をもとに、全国の相場や地域差を見ていきましょう。
■全国平均とローン事情のリアル

総務省の「住宅・土地統計調査」によると、全国の持ち家世帯の約7割が住宅ローンを利用しています。 返済額の中心は月9〜11万円前後で、無理のない範囲に収めている家庭が多いようです。
家の価格だけでなく、ローンと生活費のバランスを取ることが大切。
数字は冷たく見えますが、実際は“暮らしの目安”としてとても参考になります。
■首都圏と地方、費用の差はどれくらい?
不動産経済研究所の調査では、2023年度の首都圏新築一戸建ての平均価格は約4,600万円。
土地代が高い都市部では費用が上がりやすく、 同じ規模でも郊外や地方では3,000万円台で建てられることもあります。
「少しエリアを変えたら予算に収まった」という声も多く、家の価格は建物だけで決まらないことがよく分かります。
■“安く建てる工夫”は、今や当たり前
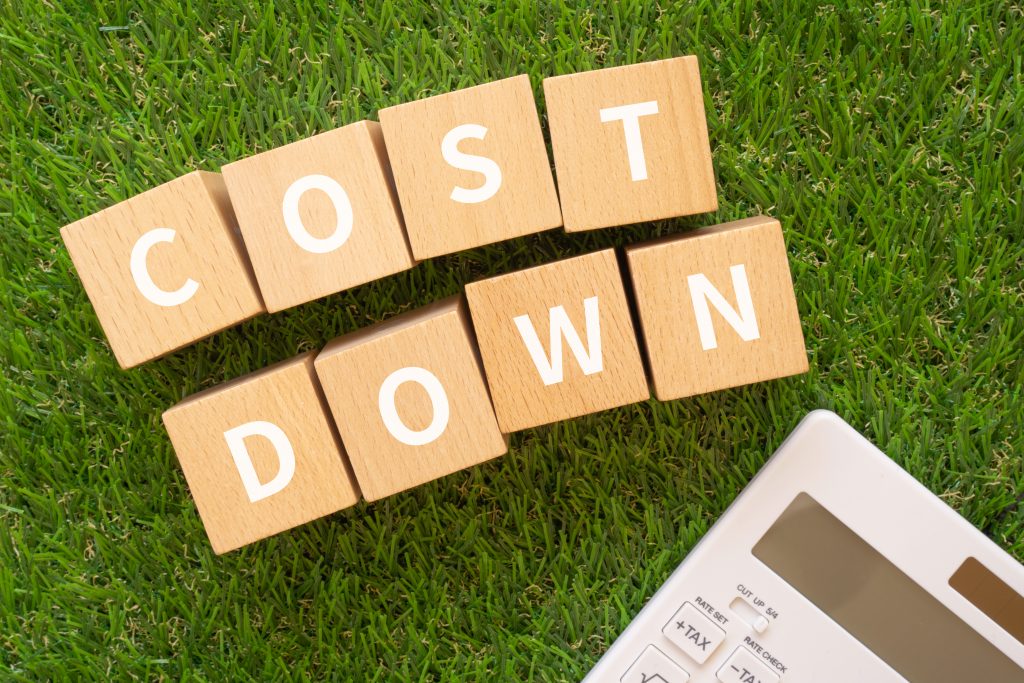
リクルートの「注文住宅トレンド調査」によると、建築費の中心層は2,500万〜3,500万円台。
多くの家庭が間取りをシンプルにしたり、標準仕様を活かしたりして費用を抑えています。
「安く建てる=妥協する」ではなく、「工夫して建てる」時代になっているのです。
データが教えてくれる“現実的な家づくり”
これらの数字が示すのは、安く建てることが特別ではないという現実です。
大切なのは金額より、自分たちの収入や暮らしに合った計画を立てること。
ローン・土地・設計のバランスを整えることで、 数字の裏にある“安心できる暮らし”が見えてきます。⑦
実際の家づくりから学ぶ|費用を安く抑えた人の工夫例
「工夫すれば家を安く建てられる」と言われても、 実際どうやって実現したのか気になる方も多いでしょう。
ここでは、無理をせずに“費用を抑えた家づくり”を叶えた人たちの例を紹介します。 共通しているのは、我慢ではなく工夫で節約したという点です。
■時期をずらして100万円以上の節約に成功

30代の共働き夫婦は、春の繁忙期を避けて冬の閑散期に契約を決めました。
同じプランでも見積もりが約120万円下がり、「まさかここまで違うとは」と驚いたそうです。
担当者も「閑散期は職人や設備の調整がしやすく、柔軟な見積もりが出しやすい」と話していました。
少し時期をずらすだけで、家づくりの予算が変わる好例です。
■間取りの整理でコストも暮らしやすさもアップ
別の家庭では、当初4LDKだった間取りを3LDK+多目的スペースに変更。
「子どもの成長に合わせて後から仕切ればいい」と考えた結果、建築費は約80万円ダウン。
動線も短くなり、「掃除が楽」「家族の気配が感じやすい」と好評でした。
間取りを減らすのではなく整える発想が、結果的にコスト削減につながっています。
■補助金と低金利ローンを上手に活用

子育て世帯では、補助金制度と住宅ローン控除を併用して初期費用を抑えた例もあります。
「手続きは難しそうと思っていたけど、住宅会社がサポートしてくれて助かった」との声も。
制度を知り、活かすことも立派な節約術です。
■長期目線で“安く暮らせる家”を実現
ある家庭は断熱性と耐久性を重視した仕様を採用。
初期費用は少し上がりましたが、光熱費が減り修繕サイクルも長くなり、
10年後には差額以上の節約に。
「建てるときに考え方を変えただけで、あとが本当に楽だった」と話しています。
無理をせず、自分たちのペースで

どの事例にも共通しているのは、削るのではなく整える姿勢。
時期・間取り・資金計画──少しの工夫で結果は大きく変わります。
家づくりは競争ではありません。
大切なのは、自分たちに合う“ちょうどいい形”を見つけること。 その積み重ねが、最終的に「賢く安く建てる家」へとつながります。
よくある質問|家の費用を安く建てるための疑問解消
Q. 家を安く建てると、耐震性や安全性が下がりませんか?

よくある不安のひとつですが、建築基準法を満たしていれば構造上の安全性は確保されています。
“安く建てる”とは、材料を減らすことではなく、設計を工夫してムダを省くこと。
複雑な形を避けたり、標準仕様をうまく使うだけでもコストを抑えつつ安心できます。
信頼できる住宅会社を選び、耐震等級を確認しておくとより確実です。
Q 注文住宅と建売住宅、費用を抑えるならどちらがいい?
どちらにもメリットがあります。
建売住宅は資材をまとめて仕入れるためコストが下がりやすく、価格が明確。
一方で、注文住宅は自由度が高く、不要な仕様を省けば結果的に安くできることもあります。
大切なのは「自分たちの暮らし方に合うかどうか」。
そこを軸に考えれば、どちらの選択でも失敗しにくくなります。
Q 初期費用を抑えると、あとで修繕費が増えませんか?

たしかに、安さだけを優先すると後の費用がかさむケースもあります。
外壁や屋根のグレードを落とすと、10年ほどで再塗装が必要になる場合も。
ただ、耐久性の高い素材を選べば、メンテナンスの周期を延ばせます。
“安く建てる=短期の節約”ではなく、“長く得する家”を意識して判断することが大切です。
Q. どの段階で予算オーバーになりやすい?
多いのは、土地購入後や仕様を決めたあとの段階です。
外構・照明・登記費用など、見積もりに含まれない項目が追加されやすい部分です。
予備費を1割ほど確保しておくと、想定外の出費にも慌てず対応できます。
見積書を見るときは、「何が含まれていて、何が別費用なのか」を必ずチェックしましょう。
Q. 家を安く建てるうえで、いちばん大切なことは?
「どこにお金をかけ、どこをシンプルにするか」を決めることです。
見た目の豪華さより、動線や快適性を優先すれば自然とムダが減ります。
“安く建てる”とは、我慢ではなく“選ぶ力”のこと。
自分たちに本当に必要なものを見極める姿勢が、満足度の高い家づくりにつながります。
まとめ|“安く建てる”ことは、賢く選ぶこと
家を安く建てるというのは、単に「費用を削ること」ではありません。
大切なのは、どこにお金をかけて、どこを整えるかを見極めること。
建てる時期や間取りの工夫、金融制度の使い方、土地選び。
さらに、建てたあとの光熱費や修繕費まで考えてこそ、 “本当に安くていい家”に近づきます。

数字の話ばかりになりがちですが、家づくりって本当はもっと感覚的なものですよね。
どんな毎日を送りたいか、家族がどんな時間を過ごしたいか。
それを考えながら決めていくと、自然と優先順位が見えてくるのだと思います。
ポラスグループ(対応エリア:埼玉・千葉・東京) のモクハウスでは、プロのアドバイザーが住宅計画をサポートしています。お気軽にお問合せください。